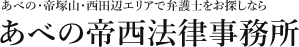弁護士が解説!遺言書があるときの相続の進め方は?
相続手続きを進める際、遺言書の有無は大きな影響を及ぼします。
遺言書があれば被相続人の意思を尊重して遺産分割を行うのが原則ですが、実際には相続人間の合意や不公平感など、さまざまな事情が絡むことがあります。
この記事では、遺言書がある場合の相続手続きの流れや、遺言書と異なる分割が可能かどうか、不公平な内容への対応方法について解説します。
遺言書がある場合の相続の進め方
遺言書が存在する場合、遺言書が有効であれば、基本的にはその内容に従って遺産分割が進められます。
ただし、遺言書には検認が必要な場合があります。
「自宅で保管されていた自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」は、家庭裁判所で検認手続きを経る必要があります。「法務局で保管されていた自筆証書遺言」や「公正証書遺言」は、検認不要です。
遺言執行者が指定されている場合は、その人物が中心となって手続きを進め、相続財産の管理や名義変更などを行います。
遺言書と異なる遺産分割は可能?
遺言書がある場合でも、遺言内容と異なる分割を行うことは可能です。
遺言と異なる遺産分割をする場合、遺産分割協議を経て分割配分を決定することができます。
その際には、相続人全員の合意が不可欠となるため、実際に遺産分割協議により遺言と異なる遺産分割を行うハードルは高いことが多いです。
また、遺言と異なる遺産分割を行った場合、遺産分割協議書を作成する必要があります。
遺言書の遺産分割が不公平な場合の対応
遺言書の内容が特定の相続人に著しく有利で、他の相続人に不利益を与える場合があります。
このような場合、相続人は「遺留分侵害額請求」を行える場合があります。
遺留分とは、最低限保障された相続分を指し、これを侵害された相続人は補填を求める権利を有します。
遺留分侵害額請求は、相続開始および侵害を知った時から1年以内、または相続開始から10年以内に行う必要があり、期限を過ぎると遺留分の請求ができなくなる可能性があります。
不公平な遺言書に直面した場合は、早めに法律専門家へ相談することが重要です。
まとめ
遺言書がある場合の相続は基本的にその内容に従いますが、相続人全員の合意があれば異なる分割も可能です。
不公平な内容に対しては、遺留分侵害額請求を行える可能性があります。
相続トラブルなどでお困りの際は、ぜひ当事務所へご相談ください。