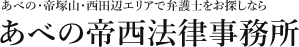遺言書の3つの種類はどう違う?それぞれの特徴を解説!
相続において遺言書は、遺された家族が円滑に財産を承継するための重要な手段です。
遺言書にはいくつかの種類があり、それぞれ作成方法や特徴、注意点が異なります。
この記事では、主な3つの遺言書について解説し、それぞれの特徴や選ぶ際のポイントを紹介します。
遺言書の種類
遺言書には大きく分けて普通方式遺言と特別方式遺言があります。
今回は一般的に用いられる普通方式遺言について説明していきます。
普通方式遺言には次の3種類があります。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
それぞれ作成方法や特徴が異なるため、メリットやデメリットも併せて紹介いたします。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者本人が本文を手書きで作成する遺言書です。
財産目録については、パソコン作成や通帳のコピー添付が認められています。
費用をかけずに作成できる点が最大のメリットですが、形式の不備があると無効になるリスクがあります。
また、自宅などで保管されていた自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認手続きが求められるため、相続人の負担になる場合もあります。
しかし、自筆証書遺言であっても、「遺言書保管制度」を利用することで、検認手続きの負担や形式の不備のリスクを回避することができます。
遺言書保管制度とは、法務局が遺言書の原本を保管してくれる制度です。
制度の利用には手数料に3900円がかかりますが、遺言書の紛失などのリスクや検認の負担を軽減することが期待できます。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人役場で公証人が作成する遺言書です。
遺言者が口述した内容を公証人が文書化し、証人2名の立会いが必要になります。
法律専門家が関与するため、内容や形式の不備による無効のリスクが低いです。
また、自筆証書遺言と異なり、家庭裁判所での検認が不要で、遺言内容の実現が確実に行われやすい点が大きな特徴です。
公正証書遺言の作成費用は、相続の価額に応じて変わるため、事前に公証役場での確認が大切です。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、内容を秘密にしたまま遺言の存在を公証人に証明してもらう方式です。
遺言者が自分で作成し署名捺印した書面を封印し、公証人と証人2名の前で手続きを行います。自筆証書遺言と違い、署名部分以外はワープロ作成や代筆でも構いません。
内容を他人に知られたくない人に向いていますが、家庭裁判所での検認が必要な点や、形式不備による無効リスクが残ります。
まとめ
遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、 それぞれにメリットとデメリットがあります。
費用や安全性、秘密保持の度合いなどを踏まえて、自身の希望や状況に応じた形式を選ぶことが大切です。
もし相続のトラブルでお困りの際は、当事務所へご相談ください。